
先日、ゲストスピーカーとしてお招きいただき、「子どもの被害と加害、そして更生へ…」というテーマで、環境人間学部で子どもの環境論を学ぶ学生たちにお話をしてきました。
私のミッションとしては、ニュースで見るような加害事件の背景として、被害の実態があることに思いをきたしてもらうことです。
その被害と加害のつながり、虐待と非行の関連性について、構造として理解していただくことに主眼がありました。
ここではその概要と記録し、お伝えします。

被害と加害、虐待と非行のスパイラルを説明すると上記図のようになります。
家庭内で虐待が起きると、家庭には常に緊張感がつきまとうことになります。居場所がなく、回避的な行動をとるようになります。まずは家出や金品の持ち出しなどの行動として表出することになります。このような行動は理解者から見ればSOSのサインであるとも言えるわけです。
しかし、なかなかそのような理解を得ることはできません。日常的に虐待をするような親であればなおさらです。そのため、さらに「しつけ」と称した虐待がスカレートするリスクがあります。それによってさらに非行行為もスカレートしていきます。
力や暴力を物事を解決する手段として学習し、他者や周囲に対して暴力的攻撃的な行為に及ぶ非行、自尊心が低いが故にその攻撃性を自らに向けて性的に逸脱したり、薬物に依存したりする行為に及ぶ非行につながっていきます。


「健やか親子21検討会報告書」によると、虐待の原因として指摘されているのは、以下の4点です。
①多くの親が子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと
②生活にストレスが積み重なって危機的状況にあること
③社会的に孤立化し、援助者がいないこと
④親にとって意に沿わない子であること
実は親自身も元被害者であり、親というもののモデルがないからこそ、虐待という方法を正当化してしまいガチになります。また、経済的な理由などでストレスが高くく、周囲に協力者や支援者もいなければ閉鎖的な空間で虐待に発展することがあります。そして、親のコンプレックスなどで子どもへの期待が年齢には不相応に過度だとそれに対する虐待行為が行われるリスクがあります。

このような虐待に関連して、子どもの成長に大きな影響をもたらすものが「愛着障害」です。
この「愛着」というものは、何となくわかるようでわかりにくいものですが、「発達性トラウマ障害と複雑性PTSD」の以下の説明が分かりやすいです。
「くっつき行動は0歳後半から2歳代の乳幼児が不安に駆られたとき、養育者にくっついて「安心」をもらいために行われる。この時期は、探索が始まる時期でもある。新しい世界に夢中になって探索するうちに子どもは不安に駆られ、養育者のところに駆け戻る。そして、くっつくことで安心を提供され、再度探索に出かけていく。この行動が繰り返される過程で、養育者の存在が幼児のなかに内在化され、目の前に存在しなくても、そのイメージを想起するだけで、不安に駆られなくなっている。これが愛着の形成である。」
このような意味での愛着をイメージした時、これが満たされなかった子どもへの影響は計り知れないと思います。
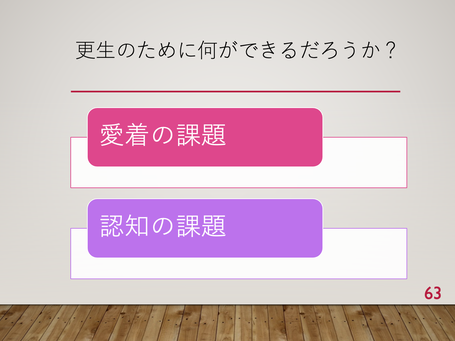
このように虐待と非行の関連性、愛着による影響を考えた時、更生のために何ができるのでしょうか。
大きな課題は、愛着と認知ではないかと考えています。
愛着障害にせよ、認知の歪みにせよ、決して一長一短で改善していけるものではないでしょう。
また1人の個人の支援のみで解決できるものでもありません。何重にも掛け合わせてシステムと複数の角度からの支援によって更生に向けた的確な支援ができるものと思います。
だからこそ、その課題を広く知ってもらうことが、何よりも必要な第1歩になると考えています。



